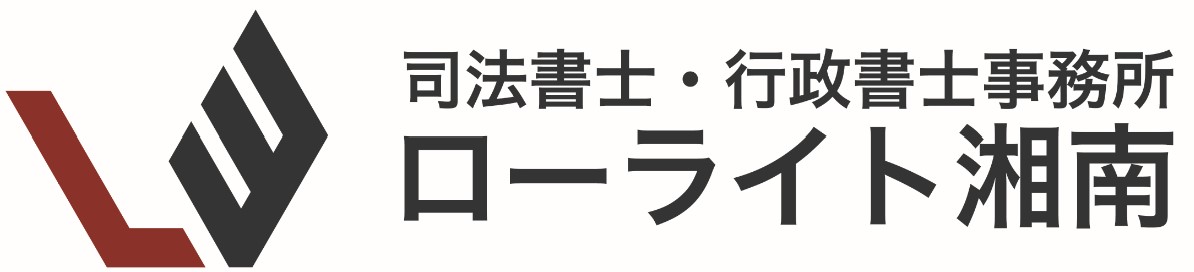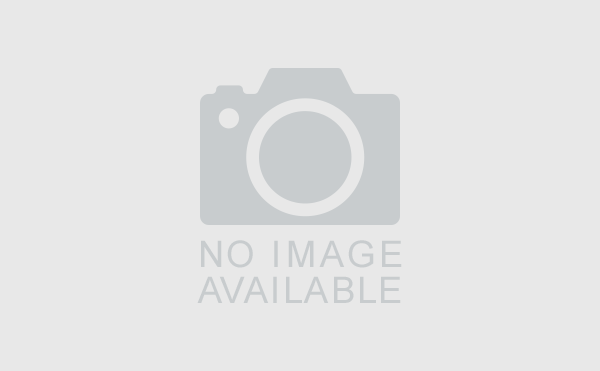相続においての信託の活用2
代表の成川です。
師走はやっぱり忙しいですね。今日は役所にいったりして夜から面談でした。
あまりお客様の迷惑にならないようなスケジュールを組みたいと思います。
さて前回の続きです。
相続での信託の活用ですがまず信託自体が何なのか分かりづらい点はありますよね。
信託とは簡単に言えば「財産を預けて管理を誰かにしてもらい収益を誰かにあげる」ということです。
預ける人を「委託者」、管理する人を「受託者」、収益をもらうひとを「受益者」といいます。
これが相続にどのように使えるかということについて簡単な一例をあげてみます。
まず、自分が生きてる間に家賃収入のある不動産を家族や親しい人に預けます。
この預けた家族や親しい人が「受託者」として管理してもらい、自分が生きている間
には自分を「受益者」として家賃収入をもらいます。
そして管理をしてもらう人との間の契約で自分が死んだときやその後の「受益者」をどうするかといったことを自由に契約で決めておきます。
その結果自分が死んだあともその契約のとおりに財産の収益を得る人が移っていきます。
信託のいいところは自分の相続だけでなく、自分の相続後のことも自分の意思を反映できるところですね。
例えば自分が死んだら妻に、妻が亡くなったら姪にという指定も可能になります。
このような指定は遺言ではできないので家族信託が役に立つ場面です。
1980年生まれ。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了後、研究所研究員、プロギタリストを経て司法書士・行政書士として「司法書士・行政書士事務所 ローライト湘南」を運営。専門は法人設立、融資サポート、営業許可、不動産活用。法令知識と経験で企業の問題解決のコンサルティングを行ってます。
LINEでお得な補助金・給付金情報を配信しています!
ローライト湘南のLINE公式アカウントで最新のお得な補助金・給付金関連情報を発信しています。
・コロナ対策の融資、補助金、給付金の最新情報が知りたい
・会社で使える補助金を教えてほしい
・融資で役立つ情報がほしい
・会社の設立、登記、各種手続きについて相談したい
といった方はぜひ友だち登録をお願いします!
・コロナ対策の融資、補助金、給付金の最新情報が知りたい
・会社で使える補助金を教えてほしい
・融資で役立つ情報がほしい
・会社の設立、登記、各種手続きについて相談したい
といった方はぜひ友だち登録をお願いします!